
ロジスティードの半澤 康弘氏と、Logpose Technologies CEOの羽室 行光が、拠点横断の中央管理構想を実現するPoCを通じて見えてきた物流DXの可能性と、業界変革へのアプローチについて語り合いました。
本記事では、PoCの狙いと手応えを起点に、物流業界が直面する構造的課題、その解決の糸口としてのテクノロジー活用、そして今後の挑戦について深く掘り下げます。
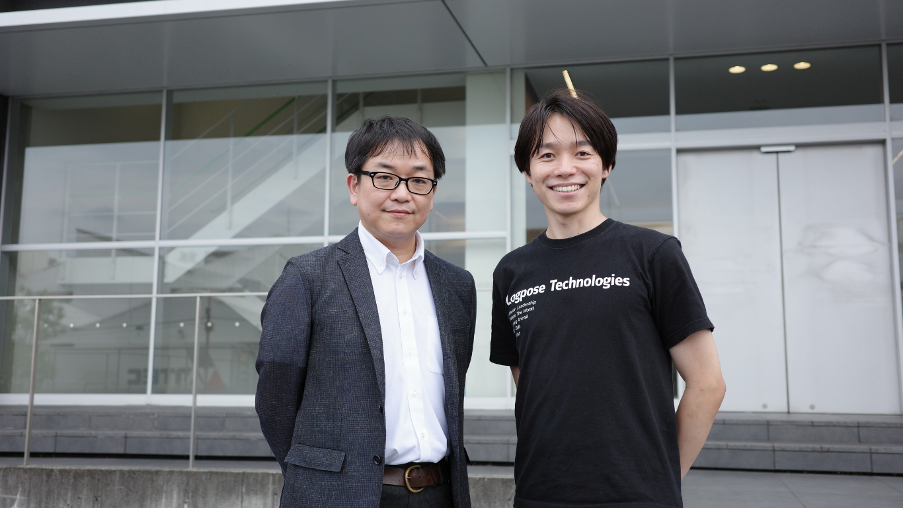
【対談者】
- ロジスティード株式会社 DXソリューション開発本部 サプライチェーンイノベーション部 部長 半澤 康弘
- Logpose Technologies 株式会社 CEO 羽室 行光
目次
【取り組み概要について】
今回の取り組みは、ロジスティードの配送実績データを活用し、Logposeの自動配車システムと分析力を用いて実施した「複数拠点の中央管理」をテーマにしたPoC(概念実証)です。
中央管理によって目指すのは、以下の3点です:
- 営業強化:どの拠点がどの案件を受注すべきかが明確に把握できる状態
- 拠点間連携:運びきれない案件や空き車両情報を各拠点で共有し連携する体制
- 集中配車:全拠点の配車データを俯瞰し、全体最適に基づく差配を行う仕組み
今回のPoCは、実運用に向けた初期ステップとして、拠点横断での配車最適化や空きリソースの可視化効果をシミュレーション・検証したものです。
1. 物流業界が直面する構造的な課題と今こそ求められる変革
羽室: 今日はよろしくお願いします。まずは業界課題の認識を合わせるところからはじめさせてください。物流業界全体としてどのような課題を抱えていると感じていますか?また、それに対して何を変えていくべきとお考えですか?

半澤氏:
日本の物流業界は、経営基盤の弱さ、ドライバーの待遇格差、そして輸送領域におけるデータ整備の遅れといった、構造的な問題を長年抱えています。とくに中小・中堅の運送会社が地方を中心に多くを占めている現状では、輸送の価値が正当に評価されにくいという側面があります。
これまで主に語られてきた「効率化」や「コスト削減」ではなく、「共存共栄」を軸にしたサプライチェーン構築へ転換すべきタイミングに来ていると考えています。そこには、企業間連携とネットワークの最適化が不可欠であり、質の高いデータを起点にした取り組みが必要です。
2. 「拠点横断の最適化」という挑戦──PoCで見えた中央配車の可能性
羽室: この課題を背景に、今回のPoCの取り組みがあると思うのですが、改めてPoC取り組みのきっかけを教えていただけますか?
半澤氏:
今回のPoCの出発点は、「ネットワークの全体最適」ができていない現実でした。多くの拠点がそれぞれのKPIや営業目標に基づいて最適化を図っており、結果的に横の連携が難しい状態になっていたのです。そのため、どこか1拠点だけではなく、複数拠点の実績データを集約し、一元的に分析・差配できる仕組みが必要でした。
羽室: 実際に取り組まれて、成果として手応えはありましたか?
半澤氏:
はい。「現場目線でいかに素早く効果を出すか」という観点で非常によく構成されていました。実際の輸送現場の事情を考慮した設計がされており、期待以上の成果が得られたと感じています。実際にいただいたアウトプット資料は社内の経営層にも共有しましたが、ROIに厳しい経営層からも高い評価をいただきました。

3. 見える化 × 自動化の力──PoCが示した定量成果
羽室: 喜んでいただけてよかったです。具体的に、どのような点が成果として評価されたのでしょうか?
半澤氏:
拠点横断で配車した場合の改善数値が明確であり、「複数拠点の中央管理」のポテンシャルが感じられました。特に秀逸だったのは、自動配車システムを通じて「空間」や「空きリソース」を可視化し、それを活用した次の案件獲得戦略に接続できるような仕組みです。どこで車両が余り、どの時間帯・地域で追加案件が受けられるかが明確になれば、営業活動にも直結します。
単にシステムを作るだけではなく、それを事業にどう繋げるかという視点が、Logposeさんの大きな強みだと感じました。

4. 「現場に落とし込むこと」とは──運用への移行と「文化づくり」
羽室: 一方で、仮想環境上のシミュレーションが中心でしたが、今後これを実運用に落とし込んでいくにはどのような課題があると感じていますか?
半澤氏:
最大のハードルは「オペレーションとの接続」です。データ更新のタイミングが拠点ごとに異なると、集中配車の実行性が損なわれます。たとえば「毎朝9時時点でのデータを基準にする」といった、ルールの標準化が必要だと感じています。
また、アジャイル開発で柔軟に進められるLogposeさんのアプローチは、現場のリアルによりそって改善を進める上では非常に重要で、まさに当社のシステム開発部門にも根付かせていきたい文化の一つです。
半澤氏は続けて、「従来の発想の延長ではなかなかたどり着けない改革の前進のため、Logposeさんのようなパートナーに入ってもらうことも目的だ」と語っています。

5. 外部パートナーの意義──Logposeが果たす役割とは
半澤氏:
ロジスティードグループでは、会社の経営理念と経営ビジョンを日々の業務に具体的に反映させるための成功要件として、「現場力×見える化」を掲げています。しかし自分たちの努力だけでは見えないものもある。だからこそ、抽象度を一段引き上げて全体を俯瞰できる視点や、新たな文化を社内にもたらしてくれる外部の力が重要だと感じています。
羽室:ありがとうございます。そう言っていただけて光栄です。私たちも、特に物流業界においてはアジャイル開発の考え方が非常に相性が良いと感じています。
というのも、物流の現場は繊細な調整が日常的に求められる世界です。システムを一方的に作って「これを使ってください」と押し付けるやり方では、現実にはなかなか根づきません。
だからこそ、現場で実際に使ってもらいながら、フィードバックを受けて柔軟にアップデートしていく。この“現場と一緒に作っていく”姿勢こそが、アジャイル開発であり、物流におけるDXの鍵だと考えています。

羽室:ちなみに、ひとつ驚いたことがありまして、ロジスティードさんのような大手企業では、すでに運送領域の仕組み化は完成されているのだろうと、勝手に思い込んでいました。でも実際には、輸送領域の自動化については、これからが本番という段階にあるように感じました。このギャップは、どのような背景から生まれているのでしょうか?
6. いまこそ“輸送”に光を──ロジスティードのこれからの挑戦
半澤氏:
おっしゃる通りで、私たちロジスティードを含め、倉庫業務に強みを持っている大手企業はいます。
一方で、“輸送”の領域においては、全国各地の中小・中堅の運送会社が主な担い手となっており、結果として大手企業でも輸送分野の仕組み化や自動化が進まず、投資も遅れていたのが実情です。
しかし私は、まさにそこに大きなチャンスがあると捉えています。
これまで十分に注目されてこなかった“輸送”という機能に光を当て、その地位を引き上げていくことこそが、業界全体の成長を牽引する原動力になると信じています。
私たちが最終的に目指しているのは、「高品質な輸送データを活用し、継続的に最適化を実現する仕組み」の構築です。
たとえば、複数企業のデータを統合的に活用することで、数年先を見据えた共同配送センターの設立や、地域の協力運送会社も巻き込んだネットワーク全体の最適化など、より広範な視点での変革が可能になります。
このような取り組みは、単なる個社の改善にとどまらず、物流業界全体の課題解決に直結するものと確信しています。
この壮大なビジョンの実現には、企業の垣根を越えた協力が不可欠だと半澤氏は強調します。

半澤氏:
私たちは、自社だけでこのビジョンを完結させようとは考えていません。だからこそ、Logposeさんのような技術と現場感を兼ね備えた外部パートナーの存在が非常に重要です。単なるコンソーシアム的な枠組みをつくるのではなく、私たち自身が持つ影響力や調整能力を活かして、競合企業も含めた業界全体を“本気にさせる”ような仕掛けを生み出していきたいと考えています。
また、このような業界変革を本気で進めていくためには、「変革を担う人材」の存在が不可欠です。単なる業務改善の延長ではなく、企業の垣根を越えてネットワーク全体の最適化を構想し、それを現場と経営の両方に橋渡しできる存在。そうした“物流の中核人材”をいかに育てていくかは、今後の業界全体の成長にとって非常に重要なテーマです。
ロジスティードでは、そうした役割を担う荷主企業の「CLO(Chief Logistics Officer)」人材への啓蒙にも力を入れています。CLOには、単なる短期的ROIではなく、中長期の物流戦略を描き、経営層に対してその価値を訴求する力が求められます。加えて、財務や物流システムの理解に加え、現場を理解し現場と連携できる実行力が最も重要です。
多くの荷主企業から、こうした視座を持つCLOが誕生することで、日本の物流業界全体の変革が進み、業界全体を巻き込んだネットワーク最適化や大規模なシェアリングのような構想の実現可能性も高まります。
現在、荷主企業向けのCLO、CLO組織のスタッフ向けの研修プログラムの開発を進めています。日本の物流の未来を切り拓くプロフェッショナルの輩出にロジスティードとしても貢献していきたいと考えています。
羽室:ありがとうございます。まさに我々も、将来的には「CLOを輩出できる会社」になるという構想を社内で話しています。物流業界の本質的な進化には、担い手の進化が不可欠ですし、そこにコミットできる会社でありたいと考えています。ぜひ、また別の機会でもご一緒できれば嬉しいです。
さて、最後になりますが、Logposeに対して現在どのような期待をお持ちでしょうか? また、今後の協業の可能性についても、あらためてお聞かせいただけますか?
半澤氏:
Logposeさんには、単なる「システム提供者」ではなく、「文化を変えていく伴走者」としての役割を期待しています。
運送会社や荷主とのネットワークを生かし、共同配送や全体最適の取り組みを一緒に推進していく。そこに、Logposeさんの持つ技術と私たちの顧客基盤が掛け合わされれば、大きな価値が生まれるはずです。
また、PoCで見せてくれた柔軟な対応力やスピード感も非常に印象的でした。今後のプロジェクトでも、そうした俊敏さを武器に、共に業界変革を加速していければと期待しています。
インタビューにご協力いただいた半澤様、誠にありがとうございました。


